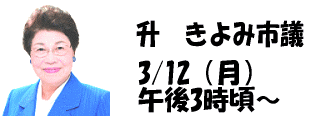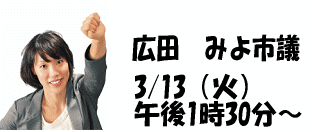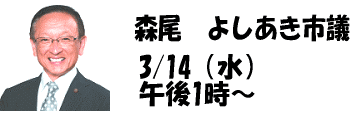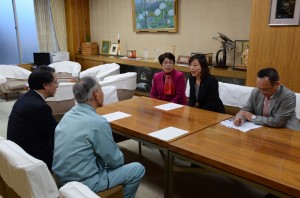金沢市議会3月議会 代表質問の全文
日本共産党金沢市議会議員 升きよみ
市長就任初めての本格予算が計上された今議会、日本共産党を代表して質問致します。
先ず市長に、めざすべき市政とは、市民のくらし安定をどの様に進めるのか所信の程伺います。
市民生活の暮らしぶりはかつてない状況下にあり、身近な企業の倒産・廃業が相次ぎ、その影響は市税収入の落ち込みや、昭和29年給付以後、過去最高の生活保護受給者3,184人の数となっていることをはじめ、賃下げ、雇用悪化 の今日、生活の糧を奪われ、人間らしい生活を取り戻せない人々が多数生まれる等深刻化しています。
の今日、生活の糧を奪われ、人間らしい生活を取り戻せない人々が多数生まれる等深刻化しています。
最もこうした実態にある、国民生活を安定させるべき政府が提案された国の予算案は、こともあろうに、全く国民を無視するもので衆議院可決となりましたが、怒り心頭に達します。
野田政権は国民に示したマニフェストを反古にして持ち出してきたのが、「税と社会保障の一体改革」とする消費税増税方針であり、既に先取り的に交付国債を発行し、先喰い的増税前提で、年金給付や子ども手当の削減をする一方で八ッ場ダム建設再開、原発推進予算維持、軍事費増額などの浪費拡大予算を提案しております。
消費税増税13兆5千億円を押しつける一方、社会保障財源を口実に子ども手当の削減4400億円、年少扶養控除廃止で4千億円、健康保険料や介護保険料の引き上げで今年だけで負担1兆円、復興増税で3600億円、年金支給開始年齢の引き上げ4年間で2兆4千億円など、国民に20兆1千億円の負担増をおしつけています。これで財政再建をはかるとしていますが、とんでもありません。
かつて消費税5%への増税が大不況の引き金となった事実からも、今、消費税増税をしたならば、ただでさえ落ち込んでいる内需を更に落ち込ませ、国内投資を更に減らし、産業空洞化、雇用減を深刻化させる悪循環の引き金となることは必至です。
我が党は、消費税に頼らなくても18兆円から21兆円の財源があることを具体的に提案しています。それは、浪費型の巨大開発、原発推進や、米軍への思いやり予算、政党助成金などのムダづかいをなくすと共に、富裕層・大企業への減税をやめ、また、証券優遇税制の最高税率引き上げ、富裕税の創設などです。
市長!「税と社会保障の一体改革」が自治体はもとより、何より市民生活の負担増をもたらすもので、こうした国の悪政に対して、その防波堤となり金沢市民のいのちとくらしを守り、市民の福祉の向上を行うには、明快に反対表明を行うべきではありませんか。市長の見解を求めます。
ところで、今度の提案が、生活の困難と厳しさを有す特に年金者、若年子育て世帯、シングル世帯等、最も弱者である方々を直撃していますが、そこに加えて、こともあろうに本市が、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の引き上げを提案したのですから大変です。
「一生懸命働いて、40年間年金納めてきて、手にする額は月65,700円の老齢年金でやっと生活している。この10年間(受け取る)年金は下がり、(支払う)国保料や介護保険料等は上がる。私らにとっては今度の(保険料の)引き上げは本当、年寄りは死ねと言われるような仕打ちだ。」と言われた高齢者の方々の声は市長に届いていませんか。どれ程に当局が国保会計に一般会計より12億円、介護保険会計に介護給付費準備基金から1億円の繰入れをしている。後期高齢者医療制度は、広域連合によるもので応分負担しているとおっしゃっても通りません。市長(14億2,300万円にわたる)市民への新たなる負担増をさせないという確たる思いがあるならば、引き上げを回避することが可能であったと思います。市長はそうした考えをお持ちになりませんでしたか。生活弱者の方への思いを何処におきましたか。
市長、貴方が「市民の政治への閉塞感や不安を払拭する」とおっしゃるのなら、安心してくらし、安心して住み続けられるまちの主人公である市民の生活を守ることではありませんか。どれ程に市民に負担増とされるのか伺っておきます。
質問の第2点、市民の安全・安心に備え、防災計画のみなおしに当たって、原発対応、震災がれきの受け入れの可能性調査に関してです。
3.11から1年、福島原発事故を踏まえて、ようやく、地震、津波、原発災害への備えが本格化されようとしています。
今も福島から80km圏内の上空に放射性セシウムがあるとのニュースや北陸電力のストレステストの評価結果からも心配が拡がっています。
能登半島地震の4倍の揺れや15mの津波に耐えるとしていますが地震の長さや揺れの想定、そして活断層の影響、そのものに、問題があることが指摘されるなど、ストレステストが安全の保障でないことも明白で依然と原発の不安に強いものがあります。国がストレステストを原発稼働の条件として新たな安全基準を出しておりますが、原発立地地域や国民の間では、とても受け入られないとしており、ますますその声は広まっております。
本市は志賀原発から50km圏内、いわゆるPPZ(放射性ヨウ素防護区域)に入りますが、石川県は本気で志賀原発から県民の安全を守り危機管理に備えていただけるのか、率直に言って谷本知事の国の対応待ち姿勢にいらだちを憶えながら、山野市長が原発災害にどう備え、どう市民の生命を守る先頭に立たれるのかに注目をしております。
①市長!なによりも最大の防災は志賀原発の再稼働を許さないこと。この立場を表明されることではありませんか。又北陸電力に強力に働きかけて下さい。決意を伺うものです。
②いよいよ危機管理体制を強化され防災計画の策定に入りますが、地震・津波の専門家にとどまらず、放射能汚染に備えた専門家や市民参加のもとで策定されるべきです。
③最悪事態に備え、ヨウ素剤の備えがようやくされることになりました。広く市民に配置場所、服用方法等知らせるべきです。
④放射能測定器も購入され、大気汚染調査を年1回実施することにしましたが、回数増を含めきめ細かく行うこと。また、市民がのぞむ場所や土壌や食品などの調査も実施すること。そして市民の要望の強い学校給食の放射能検査を行い、安全確保、食材の産地公表、情報収集と提供、などがなされるべきと考えます。
次に、震災がれき受け入れ可能性調査についてです。
輪島市のがれき受け入れ表明から一気に県民の関心が高まると同時に本市も受け入れ可能性調査を実施すると表明がされました。
被災地の災害廃棄物の処理が進まず、復興を遅らせている事は紛れもなく、今も宮城県では通常の約11年分、福島県では約3年分等、岩手県を含む3県の合計推定では日本全国の約半年分があるのですからことは深刻です。環境省は災害廃棄物の広域処理推進ガイドラインを策定し、搬出側が事前に測定し、焼却処理した場合の放射線セシウム濃度の濃縮率を計算して1kg当たり、8000ベクレル以下であれば受け入れ良し、としましたが、しかしこれまで原子炉等規正法では100ベクレルと言ったり、その数値が如何にあいまいか。国民が納得できるものではなく放射性物質への不安から当初受け入れ表明していた自治体も再検討する所が増え続け、あらためて国は地方自治体に受け入れ協力を求めております。
被災地の復興のためには災害廃棄物の処理は不可欠でありますがしかし、放射性物質に汚染された廃棄物については、安全性や環境面で様々な懸念を持つのは当たり前で、それこそ実際の受け入れとなると不安を持つのは当然です。今日の事態を招いた最大の責任は東電や国にあり、そこがなんらの責任も負わず解決策を示さないことにも不満が募っています。政府はそうした国民の不安に応えることです。市長!市長も政府に対し、国が責任を持って処理する解決策を行うことを真っ先に求めるべきではありませんか。
市長!市長は今回の受け入れの可能性調査に当たって、オールジャパンで対処とのことですが、積極的に受け入れやに、見受けますが、それにより輪島市などからも働きかけがある様ですが、放射線量等の影響などにどう対応されるか、市民への十分な説明と理解を得られると判断されているのですか。
がれきの処理に当たっては分別から始まり、埋立場処分、焼却、焼却灰や汚泥処理に至る全ての施設周辺地域に至り、又、線量基準値の考え方、正確な測定、運搬時の安全性の確保等々課題山積みですが、そうした問題への検討をどのように考えておられるのか。
本市の新環境エネルギーセンターや戸室埋立場等での受け入れをした場合、住民の合意を得られると判断されますか。伺います。
市長、少なくとも、市民の合意なき状況下では一方的に強行すべきでないと考えますが、御所見をお聞かせ下さい。
質問の第3は、地域経済の活性化にむけて――地元の企業を如何に守り、企業呼び込み型から地元企業応援型に力を注ぐか、その立場から伺います。
住みよい都市でこそ経済は発展し、都市の力と経済を豊かにしようとするなら、内需拡大をはかり、コンパクトシティをめざし、安心してくらし住み続けられる街であることは、言うまでもありません。本市は企業誘致の工業団地として金沢テクノパークを、又、地元企業を中心にした企業立地の為の安原異業種工業団地、いなほ、かたつ工業団地を造成し、分譲してきました。今回新たに河原市流通工業団地の造成事業に着手し、(24億4,255万円)をもって用地取得、造成工事に入ろうとしています。しかし、ご承知の様にこれまでの工業団地が、いまだに売れ残っております。安原工業団地は97%とほぼ完売に至っていますが、テクノパークは残り25%、いなほ工業団地は21%、かたづ工業団地については、昨年度、分譲価格引き下げしながらも、まだ53%が売れ残っております。
河原市流通工業団地造成事業は、新たに物流・卸売・運輸・商業関係企業を対象に行うとしていますが、現在の景気低迷、経済情勢下にあって、果たして分譲、売却の見通しがあるのでしょうか。前市長がテクノパークに併せて計画をした事業ですが、今一度、立ち止まって事業開始を見合わせるべきではありませんか。伺うものです。
さて、公共投資は生活密着型へと進めることが肝要です。今日、住宅建設の落ち込みがあるだけに地元企業の元気を呼ぶ一助に地域経済の活性化をめざし、住宅支援制度の拡充、住宅リフォーム制度があります。本市には各種住宅支援制度がありますが、区域、目的等が限定されています。市長は現行住宅支援制度の検証をし、研究したい旨御答弁されていますが、気軽に助成制度が活用できるよう住宅リフォーム制度充実を求める声にどうお応えになりますか。(検証した結果は)如何ですか。
質問の第4点は商業環境形成指針と大友・大河端・直江等の区画整理事業についてです。
11年前に、本市は大型店の出店ラッシュが続く中で、『金沢市における良好な商業環境形成によるまちづくりの推進に関する条例』が制定されました。我が党は、国の大店舗等の野放し路線の中での自治体条例であり、自ずと限度がある上、大型店を規制するものではなく、抜け穴となって、ゾーンによる集積可能にし、大型専門店誘導であることを指摘してきました。その後のまちづくり三法も真に有効な規制となりきれず、本市の街は大型店出店が相次ぎ、今や、小売業に占める占有率は66%、7割近い状況下、そして大型店同士のつぶしあい、その上、全国チェーンのコンビニエンスストアーが増え、結局、地元スーパーがどんどん廃業に追いやられ、買い物難民が出るほどの事態にあります。
今回ようやくにして本市は「指針」の店舗面積の上限についての考え方を従来の公共の道路を隔てることにより店舗面積の上限も各々の区画で考える即ちゾーンによる集積可能であったものを、今後、公共の道路に面する店舗面積を上限とする改訂案として、これまで例えば7,000㎡の大型店舗であったものは3,000㎡になる)提案がなされました。商店街がつぶされた後での市当局の提案は、「今更、遅すぎる。」と率直な思いを致します。ところがそこへ、本市の土地区画整理組合連合会が、直江、大河端、大友の区画整理事業に限り、店舗面積の集積の上限は5000㎡とすることを求めております。
区画整理事業側からすれば、分譲を促進したい思いから「指針みなおし」を求めてきたものといえます。
ところで、大友・大河端・直江の区画整理事業は、三地区とも進捗率は、約46%にとどまっています。そもそもこの地区の区画整理の事業はいずれも海側環状線道路建設と併せて進められてきました。我が党は海側幹線道路を取りこんでのこの区画整理事業は、人口減少期に入り、地球温暖化防止、車社会からの脱却が言われ、農業再生をめざすとき、農地をつぶして、市街化促進を行うべきではないと指摘をしてきましたが紛れもなく、この事業の破綻ともいうべき諸矛盾が色々生じてきております。
① 市長、国県市と行政が地方を誘導してきた区画整理事業のこの実態に、どのように責任を取られるのか伺っておきます。併せて全体総事業費及び保留地処分、全体事業達成の見通しについてお示しください。
②区画整理組合が、用地分譲に苦戦しているとしても真に良好な商業環境を守るかが問われています。三地区のみ適用除外となれば、結局この指針が有効に働かず形骸化(死文化)するものではありませんか。少なくともこれ以上、大型店誘致はさせないという姿勢を示すことが大切ではありませんか。市長の御答弁を求めます。
③次に、今回地域貢献の促進に当たって、雇用問題等について計画提出にとどまらず、結果報告を求めることになったことを歓迎するものですが、更に中間的に行政がチェック出来る仕組みも必要ではないかと考えます。
④ところで4年前、商業環境形成まちづくり条例に記載すべきとなっていた集客施設の定義の勝馬投票発売所、場外車券売場、船券販売所のいずれもが除外されましたが、こうした施設の取り扱いについても明確にすべきではありませんか。
質問の第5点は、新幹線開業前に公共交通運輸に関してです。
1,600億円をかけての国の予算による北陸新幹線は、金沢市区間分50億7,100万円で事業が行われようとしています。いよいよ並行在来線を能登と加賀地域を結び、存続させるとして、他の公共交通機関と連携した一体的な地域交通ネットワークを形成し、石川県と県内市町等が出資して第三セクターである単独株式会社を設立し、24年度中に準備会社を設立していくことになります。今回その為の出資金が6,750万円計上され、来年度も引き続き出資し、1億4,000万円の出資による本格会社になるとのことです。
ところで、県並行在来線対策協議会の在来線経営計画を見ますと、JR鉄道資産の無償譲渡の展望や安全性について、又、採算計画について多くの疑問や問題を感じます。現在のJR資産をそのままにして、当初から利用客減を見込み採算性が全くとれない経費になることが必至の内容で、結局、重い荷物を利用者と県民への過大な負担、押しつけを前提になっております。
設備投資計画の基本的な考え方に現行資産を活用し、JRから譲渡を受けるとし、可能な限り低廉な価格とありますが、本来無償譲渡を求めるべきです。又、初期投資を90億円から100億円と想定していますが、JRは鉄道資産の簿価を明らかにしていますか。並行在来線について採算路線はJRが維持し、不採算路線は、経営判断として、切り捨てるやり方は到底納得いくものではありません。市長、当然のことながら、出資する金沢市としてもJR側に無償譲渡は勿論、施設の修繕・新型車輌の先行導入など、財政負担をしっかり求めて下さい。
JR西日本は、昨年の決算でも経常利益689億円、内部留保9,538億円等々、体力充分の大企業です。市長にその決意の程を伺います。
次に二次交通として新年度より、石川線及び浅野川線をつなげ、市民の利用促進のため北陸鉄道に対して鉄道施設整備支援に8,810万円が計上されています。
公共交通が独立採算の経営では確保できないとして、生活に必要な交通の存続が危機に達する状況の中で、白山、野々市、金沢の3市と内灘町で支援策がとられていくことになりますが、今後の北陸鉄道への協議の場に金沢市としてどのように臨まれるのか伺うものです。
財政支援だけが求められ、市民の利便性には腰重い状況では困ります。先日私は、九州 佐賀~熊本に視察に行きました。九州新幹線に接続する在来線はもとより、私鉄の電車・バス運賃の安さ、利便性から見て、金沢の更なるの改善の必要を感じました。
この際、北陸鉄道には、均一料金の拡大、又、路線の拡充等、きめ細かな運行等はかられる様、強く求めるべきではありませんか。近年、『まちなかふらっとバス』や『まちバス』と中心市街地の利便性に比べ、郊外や中心部から離れている地域から、公共交通の利便性が悪く、「是非『ふらっとバス』の様な公共バスが欲しい」と切実に求められています。
こうした要望にこたえ、地域間格差の解消を図るべきではありませんか。市長の御所見を伺うものです。
質問の最後に「参与」の起用についてです。
この度、市長から新たに官房機能を強化するためトップマネジメントを補佐する政策担当の参与を配置することが表明されました。市長ご自身がマニフェストで民間から副市長を登用することや市民ブレインで政策を決定するとおっしゃっておられましたが、今回の提案はご自身のマニフェストで掲げられたこととどのように違いがあるのですか。仙台市、富山市等を除き余り例がなく、身分や処遇はどうなるのか。行政改革が叫ばれ、人員削減を進めている中で金沢市政にこれまで例のない配置までして、政策決定の重要なポストを置かれるのですが、結局、市民からのチェックや議会のチェックを受けないポストではありませんか。
仄聞するところによりますと、市長ご自身の後援会々長の方との事、仮にそうだとしますと、市長の恩顧と言われる人事で、公正公平性が保たれず、市政運営がゆがめられ偏向的になりかねないのではありませんか。今日、市民全体がこの街をどうするか、市民のくらし全体を考え、将来未来像を創造する重要な時に、適切を欠くのではありませんか。市長の見解を求めて質問を終わります。