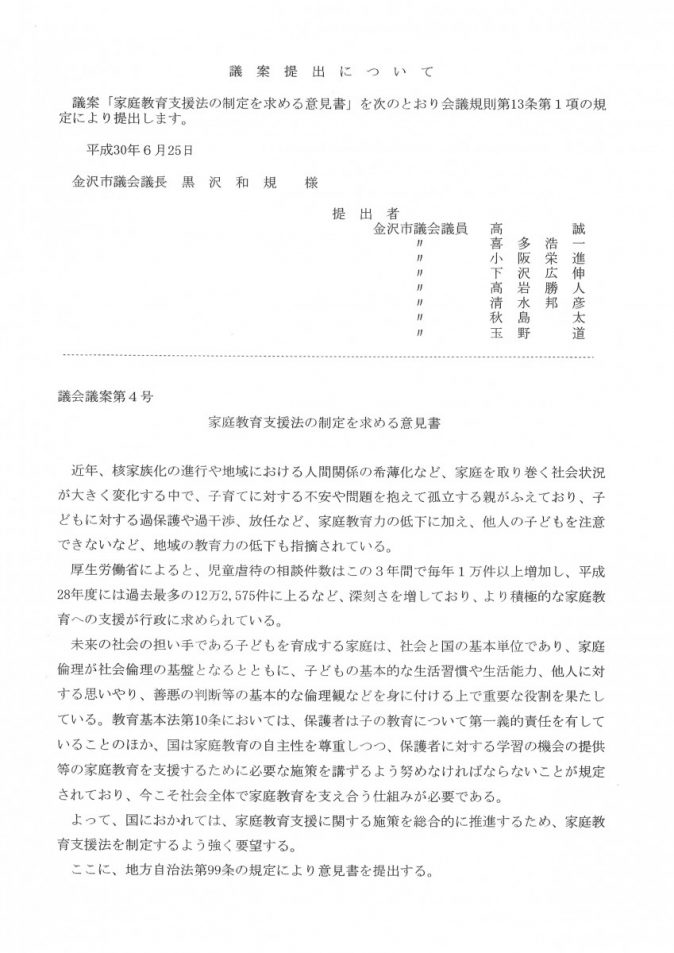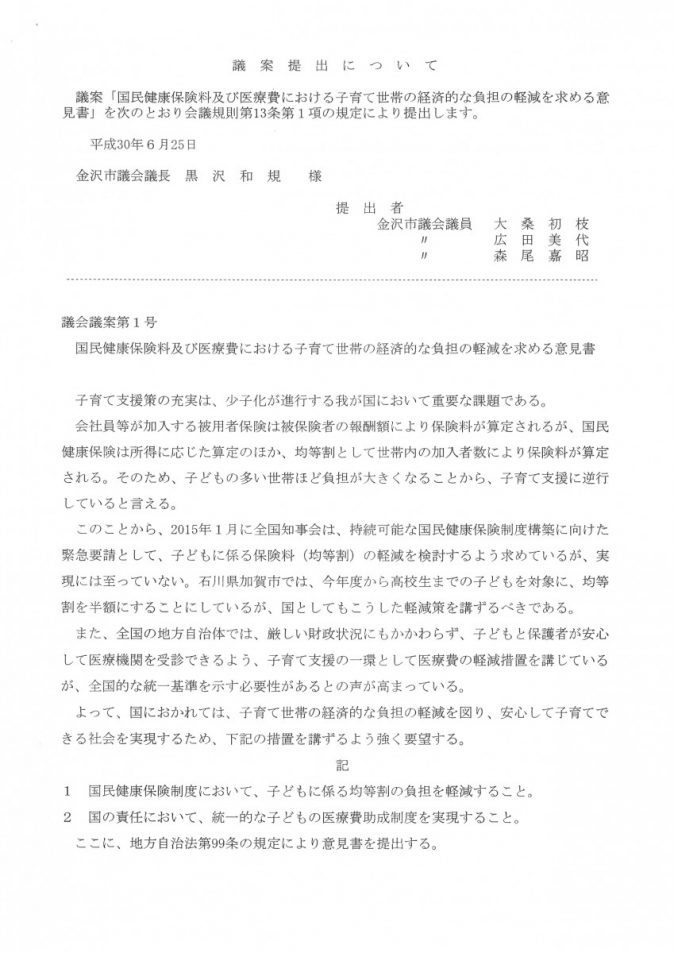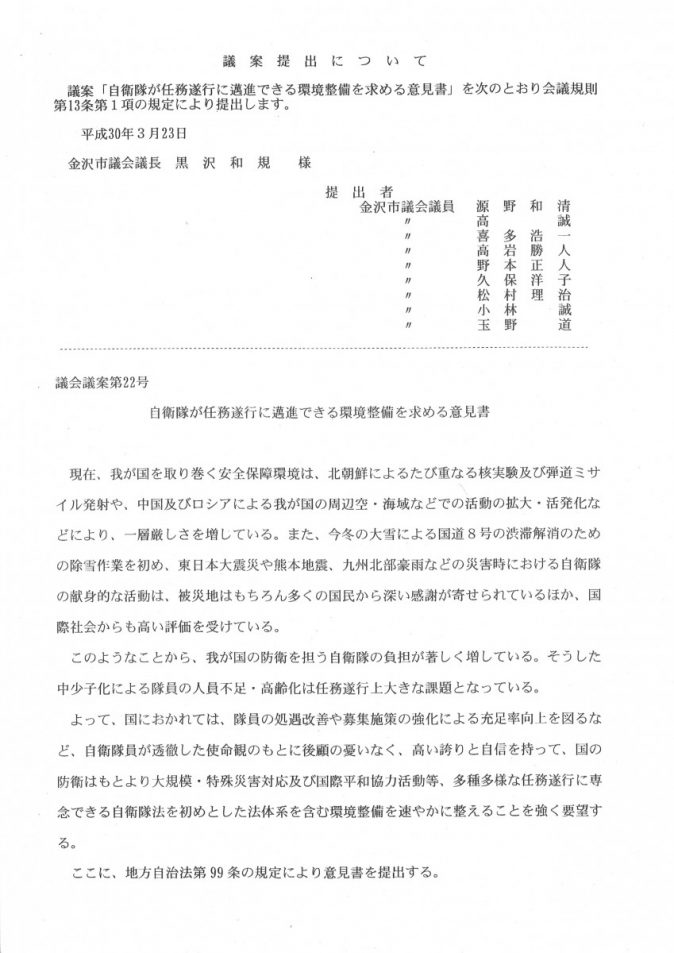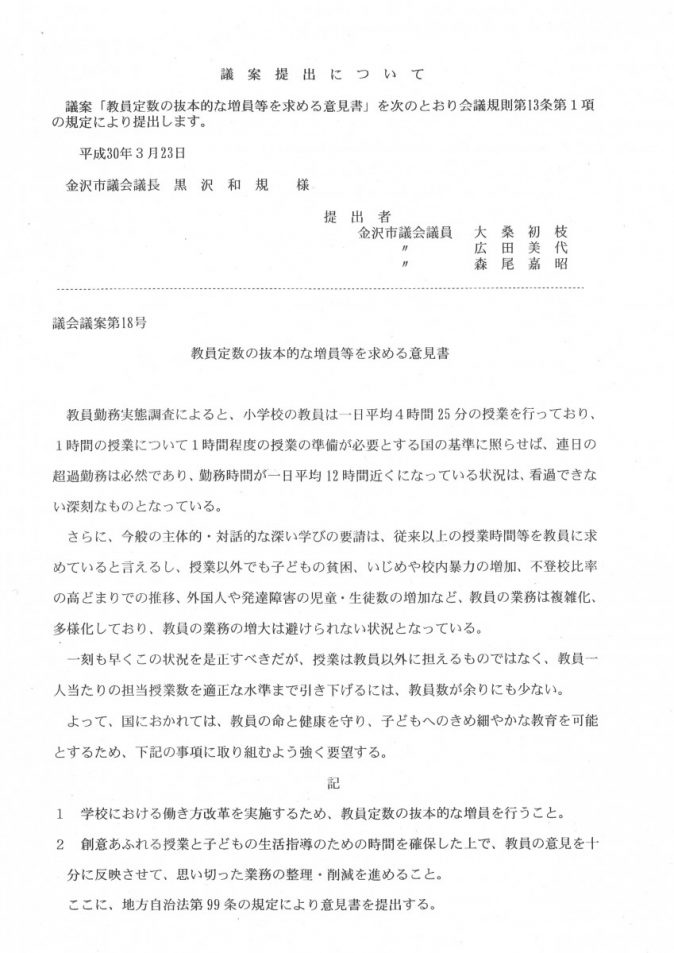- 雪害への対策について
最初の質問は雪害への対策についてです。
今回の37年ぶりともいわれる大雪は市民生活に大きな影響を与えました。公共交通の大幅な遅れのみならず、長期間にわたってバスが運休になる地域が出たり 生活道路の除排雪が進まなかったりと本市の除排雪の抜本的見直しを求める声が広がりました。
今回の大雪では、市民の命とくらしを守る雪害対策がきちんとなされたのか、そして今後何を教訓にすべきか検証が必要です。
そこで、まずは「除雪作業会議」という会議がなぜ開かれなかったのか伺います。
本市の除雪計画では、まず12月に「除雪対策会議」が開かれ、その後道路除雪作業を円滑に行うための「除雪作業本部」が設置されます。異常積雪があれば、「雪害対策本部」が設置され、今回はこの設置にいたりました。さらに、除雪作業本部長は、効率的な除雪作業を実施するために、「除雪作業会議」というものを開催することができます。この会議に参加するのは、市民のくらしに身近な、広報広聴課、交通政策課、長寿福祉、障害福祉、子ども政策推進課など福祉関係、教育総務課、緑と花の課、市営住宅課など、などです。
よって、「除雪作業会議」は市民に身近なくらしの視点で、効率的に除雪がされているかどうかを各課が共有する場であり、非常に重要な会議ではないでしょうか。
私の元には、福祉や市営住宅にかかわってさまざまなSOSがありました。保育所の保育士さんから、朝早くから保育所周辺の雪かきをして子どもの登園を待ち、帰りは道路除雪がされていなくてお迎えが遅くなった保護者を待って、夜まで保育所に残っていたという声、一人暮らしの高齢者の方からは、玄関周りや自宅敷地内の除雪すら困難な状況で 外出することもできない、又デイサービスや配食サービスの車が、利用者の方の家にたどり着くこともできないという事態も生じました。透析を受けている高齢の方が、病院まで行くことができず、週3回の透析のうち1回を休まざるを得ない事になりました。高齢者や障害のある方など多くの市民が、今回の雪で自宅に閉じ込められ、不安な思いをしていました。
また、市営住宅に住む方からは、高齢化が進み誰も除雪ができない中、「出入り口付近だけでも除雪をしてほしい」と市営住宅課に要望しても、対応してもらえなかったとお聞きしています。
こうした事例を聞くにつれ、「除雪作業会議」が開かれ、各課からの情報に基づいて対応が協議されていたならば、雪害対策本部との連携もでき、市民への対応も違ってきたのではないでしょうか。
いくらチームや会議・対策本部を立ち上げても、市民の命や福祉に直結した各課との連携や協力がなければ市民の要望に応えることができません。こうした点から「除雪作業会議」が開催されなかったことは重大です。どうして開かなかったのか説明を求めます。
今回の大雪では、農業被害も深刻です。昨日の報告では、農業用ハウスの倒壊は618棟にも及んだとのことです。わたしも雪の中打木地区へ伺い、西瓜生産者の方にお話をお聞きしました。この方のビニールハウスも雪の重みで倒壊し、無残な姿をさらしていました。その上、さらなる被害を防ぐために覆っているビニールを切断しパイプだけの状態にする作業をして何とかこれ以上被害が出ない様策を講じていました。
「もう、へとへとだ。今年は、西瓜の収穫も少なくなるのではないか。ビニールハウスを修理するといっても、お金と人手がいるから このまま立て直しをあきらめようかと思っている。春一番のふときゅうりの作付けもどうなるかわからない」と話されました。倒壊したハウスには市から三分の一が補助されるといいますが、もっと手厚い対策を講じるべきではないでしょうか。
農業関係の皆さんは、農業自体の再建ができるかどうか、県や市がどこまで支援してくれるのか不安を募らせています。
金沢市にとって大切な農業を続けられるよう、国や県とも連携して支援策の拡充を求めますが、おうかがいいたします。
②介護保険について
次に介護保険について、お尋ねいたします。
介護保険料は3年ごとに見直され、今回提案された第7期の介護保険料は、基準月額が6590円となり、保険料区分が11段階から13段階へと増えました。前回第6期の基準月額が6280円だったので、基準額310円、およそ5%も引き上げられることになります。介護保険制度が始まった2000年の基準月額3150円から年々引き上げられ、2倍以上もの金額に跳ね上がっています。第6期の本市の保険料は、48の中核市の中で高い方から4番目であり、市民からは保険料が高すぎるとの声が上がっています。また、介護保険料を払っても、必要な介護サービスを利用できない制度になっているこの状況では制度そのものへの理解が得られません。
市長、介護保険料の引きあげは、やめるべきです。
本市の財源はどうかというと、介護保険の基金は6期の間、三年間使われず、毎年の会計の黒字によって基金残高が8億5000万円にまで増加しています。この基金を活用すれば、保険料は据え置くだけでなく引き下げが可能です。市長は提案理由の説明の中で、「低所得層に配慮し基金の取り崩しや細やかな保険料段階の設定などで最小限の改定に留めた」としますが、実態は大幅な値上げであり、基金を使って引き下げを図るべきと考えますが、市長のお考えをお聞きします。
介護保険料の減免制度についても伺います。
本市の保険料の減免は、「世帯の生計を主として維持するものが死亡したり長期入院したりしたことによって収入が著しく減少した場合や事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合などに減免できる」としています。また、「家族の収入の合計が生活保護水準の1.2倍以下」という規定があり、低所得で生活が大変な方も減免の対象になります。
まずは、本市で減免制度を受けている方は何人いらっしゃるのかあきらかにしてください。そして、この減免制度は市民にあまり知られていないと感じます。この減免制度をもっと広く知らせることが必要ですがいかがでしょうか。
次に介護職員の処遇改善について伺います。
毎年、介護の実態を訴え改善を求める要望書を市に提出している、家族会の方々から今年も要望書が提出されました。その中で、切実に訴えられたのが介護職場の実態です。一般職の賃金に比べ6割から7割という低い現状から介護職の人材確保は困難な状況が慢性化しています。県内の介護職の養成校でも学生が集まらず、養成学科をやめてしまったところもあります。ある介護施設では人材確保の見通しが立たずフルオープンができないと言います。
介護職員の確保は、言うまでもなく差し迫った課題です。しかしながら、新年度予算を見ても、処遇改善の抜本的な解決策は打ち出されていません。本市独自に介護職員の処遇改善や確保対策の強化を緊急に取るべきと考えますがいかがでしょうか、お伺いいたします。
かなざわケアサポーターについてお尋ねいたします。
本市では、昨年の4月から要支援の方が介護保険の枠から外され、総合事業に移行されました。しかし、実施する事業所が少ないことや、期待されていた担い手である、「かなざわケアサポーター」の就労希望が少ないなど問題が多いものです。
そこで、現在のかなざわケアサポーターの就労状況をお聞きいたします。地域によっては事業所の経営が成り立たないとして、基準緩和型サービスの指定を受けないという事態が起こっています。わずか12時間の研修修了者にサービスを提供させるという事は、現在行っている資格者によるサービス提供の専門性を否定することにもなり、資格者の処遇の引き下げ、介護人材不足にもつながる懸念があります。
生活援助は高齢者の暮らしを支えるもの。また、自立とは、介護サービスを利用しながら自分の持てる力を活用して自分の意思で主体的に生活する事であるとするならば、生活援助も資格を持ったヘルパーさんが担うべきでかなざわケアサポーターによるサービスを進めるべきではないと思いますがいかがでしょうか。
高齢者のボランティアポイント制度についてお尋ねいたします。
昨年のモデル事業を経て、来年度本格実施するもので、65歳以上の方が特別養護老人ホームでボランティア活動をする際に時間に応じてポイントが付与されるというものです。高齢者の社会参加を促進するという意味合いはありますし、ボランティアの方々には敬意を表しますが、一方で、ボランティアをされている方から、高齢者が高齢者を援助するとはどういうことか、行政が自らの公的責任を、都合よくボランティアに押し付けるものではないかという声もあります。ボランティアは善意で行うものであり、ポイントをあげるからと言って、行政が行うのは違和感があります。ボランティアに依存するのではなく、専門職が中心に担えるように環境整備をすることこそ行政の役割ではないでしょうか。考え方をお聞きします。
次に、特別養護老人ホームの施設整備についてお伺いいたします。
高齢者が特養老人ホームを希望するのは、年金が少ない高齢者にとって頼みの綱だからです。アンケートでも、特養ホーム待機の理由に経済的負担を訴える方が多くいます。有料老人ホームやサービス付き高齢者施設等は減額制度がなく費用負担が重く、経済的にも長期間入居できないのです。
そこで第7期の施設整備について伺います。特別養護老人ホーム整備に当たっては、誰もが入居できる、待機者解消のためになる、多床室を含む施設の整備をしてほしいとの要望がありますがいかがでしょうか。
③子育て支援について
次に、子育て支援について質問いたします。
まずは、子どもの医療費助成制度についてです。本市では、市民の根強い要望を受けて、子どもの医療費は2015年7月から、入院は1000円、通院は窓口で500円払えば受診できるよう改善されました。子育て中の親御さんから大変喜ばれています。子どもの貧困問題が深刻化している今日、本制度のさらなる拡充は待ったなしです。18歳までの年齢の拡大、さらには、医療費の窓口完全無料化を求めますが、市長のお考えをお聞かせください。
子育て支援2点目は保育士の処遇改善と確保策についてです。
本市においては、近年の保育所整備などで保育所の受け入れ枠が広がりました。しかし一方で、今年も西部地域など一部の地域で希望通りに全員は入所できなかった事も報告されています。希望の地域の保育所に入れない実態を打開するための対策を進めることが緊急の課題でもあります。
保育所の新設も予定されていますが、保育士の増員で受け入れ定数を増やすことも必要です。
この間、国は保育士の処遇改善を行いましたが、これは保育士のキャリアアップ研修を条件にしたもので、職員間で処遇が異なり格差が生じないかという不安な声も出されています。公平な労働条件で保育士全体の処遇改善が必要です。このことは全体の保育の質の向上と保育士確保にもつながります。処遇改善に本気で取り組み、保育士確保の声にこたえることが求められていますが市長のお考えをお聞きいたします。
④教育について
最後の質問は、教育現場の現状についてです。
まず、教員の労働状況について、全国で教員の長時間労働が過労死ラインを超えていると報道されています。県の調査でも、小学校が月平均60・6時間、中学校に至っては平均91・6時間と過労死ラインを優に超えている実態が明らかにされました。金沢市の小学校に講師として赴任した方が1年目にして、クラスを受け持ち、公開授業もすることになりました。授業の準備や、会議、そして、発表間近になると指摘された課題に答えようと夜の10時11時まで学校に残って準備をする。その為 毎日、子どもと向き合うどころでなかったのが辛かったと言います。
教師を取り巻く環境は依然と厳しい状況があり、授業づくりや一人一人の子どもと向き合う時間の充足感が低いままでは、教育への情熱さえも失いかねません。教師は、生徒や保護者への対応、会議や報告書の作成などいろんな対応に追われています。
県の教育委員会は、教職員の多忙化改善推進協議会を設置し、業務改善に向けて取り組んでいくとしていますが、少人数学級の実現や市としても教員を増やす抜本的な取り組みが必要ではないでしょうか。お尋ねします。
この問題の二つ目に、学力テストについてお尋ね致します。
福井県では池田中学校の自殺を受けて、県議会で「教育行政の根本的見直しを求める意見書」が、賛成多数で採択されました。この福井県池田中学では、宿題はいつも学力テストの過去問であり、学力テストの成績優先の教育が行われていたとのことです。これを受けて福井県議会では、過度の学力変調を避けるとして、県独自の学力テストなどの実施を学校の裁量に任せる、という意見書をまとめました。
全国学力テストをめぐっては、日本一であり続けることが目的化し、本来の教育のあるべき姿が、見失われてきたのではないかと、警鐘が鳴らされています。
金沢市も例外ではなく学力テストの始まる前の学年の3学期ぐらいから過去問プリントが始まると言います。学力テストの結果を見て、今後の授業に生かしていくという当初の目的から大きく外れ、地域や学校間の競争を招き順位を上げるための対策は過熱する一方となっています。本市としても現場の声に耳を傾け学力テストの在り方を見直し廃止すべきではないかお伺いいたします。
教育現場では、いじめの問題も深刻です。
学校内でのいじめが全国で報道され、痛ましい事件に発展することが多くなっています。昔のように、あからさまないじめだけでなく、SNSの発達によっていじめの実態も複雑・陰湿なものへと変化してきています。
新聞報道で、小学校在籍中にいじめを受け、心的外傷後ストレス障害を発症した本市の高校生が、損害賠償を求めた訴訟を知りました。裁判長は、いじめと心的外傷後ストレス障害の因果関係を認め、学校側にも過失があるとする判決を下しました。この問題は重大であり、本市教育委員会は真摯に受け止めなければなりません。
教育長はこの件について、どのように受け止め、今後いじめの対策にどう取り組んでいくのかお伺いいたします。
いじめ対策が遅れれば、深刻な悲しい結末を迎えることにもなりかねません。速やかな実態把握に努めるとともに、いじめ対策が必要ではないか、お伺いし。わたくしの質問を終わります。
答弁
-山野市長
7番大桑議員にお答えいたします。
雪害のことですけれども、私の方からは農業用ビニールハウスの復旧支援について申し上げます。今回補正予算に800万円を計上しており、現在被害と復旧費用の把握にも改めて努めているところであります。県や国の支援につきましては、今後の動向を注視をし情報の把握に努めていきたいと考えています。市として適切に対応をして参ります。
介護保険料のことについてですけれども、介護給付費準備基金を取り崩して保険料の引き下げに力を尽くすべきだということでありました。おっしゃる通りでありまして、全額取り崩しを今回させていただきたいというふうに思っています。この度、介護保険料改定に際しましては、高齢化の進行で介護サービスの利用が増えることに加えまして、事業者に支払う介護報酬がこの4月から0.54%引き上げられることに伴い、サービス給付費の増加が避けられない中、今ほど申し上げました介護給付費準備基金を全額活用することにより引き上げを最小限に留めたところであります。ご理解をいただければと思います。
減免制度がまだまだ知られていないのではないかというご指摘でありました。市民向けのパンフレット、保険料納入通知書に同封するチラシへの掲載により周知に努めてきたところであります。保険料の納付が滞っている方に対しましては、催告などに併せまして減免制度に関する丁寧な説明を行ってきているところでもあります。今後とも保険料の納付が困難な状況にあります被保険者の負担軽減に繋がりますよう、制度の周知に努めて参ります。
介護職員の賃金のことですけれども、介護職員の賃金改善に関しましては、国が事業者に支払われる介護報酬の見直しの中で必要な措置を講じていくというふうにおっしゃっておられます。今後の動向を注視して参りたいと思います。
ケアサポーターのことについてですけれども、本年2月末現在、ケアサポーター養成研修修了者のうち、基準緩和型訪問サービスに従事している方は7名であります。基準緩和型訪問サービスの利用者は増えていますので、今後事業者の理解を求めていきながら、ケアサポーターの就労支援を図ってまいります。
ボランティアポイントのことについて、ボランティアに頼って人材育成という責任をしっかり果たしていないのではないかというご指摘でありました。介護人材の確保におきましては平成27年度より市内介護サービス事業所の職員を対象としたケアワーカーカフェを開催し、職場環境の改善等に資するための情報交換の場を提供してきた他、明年度より若手職員が働きやすい職場環境の整備に向けまして介護サービス事業所が新採職員のサポート体制を構築するための研修開催費等への助成を予定をしているところであります。介護人材の確保は喫緊の課題であるというふうに思っています。今後とも、今まで申し上げました事業者であったり介護職員のご意見もお聞きをしながら、本市もしっかりとその施策に取り組んでまいります。
多床室を設ける特別養護老人ホームのことについてですけれども、入居者の人権尊重とプライバシー保護の観点から、個室による整備を推進する旨、国が方針を示しているところであります。そうした国の方針に基づき整備を進めているところであり、多床室による特別養護老人ホームの整備は今のところは考えてはいません。
こどもの医療費の助成についての拡大のご提案をいただきました。平成26年10月、対象を中学校3年生まで拡大し、平成27年7月、現物給付化をしたところであり、窓口負担の無料化や年齢の拡大は今のところは考えてはいません。
また、子育て支援の中で保育士の処遇改善のことについてですけれども、国においては昨年12月閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において2019年度に保育士の賃金を引き上げるという方針が打ち出されています。また先ほど現行の処遇改善加算について明年度から対象者を広げられるように見直すことが示されたところであり、本市独自の新たな処遇改善は考えてはおりません。
-磯部 土木局長
除雪作業会議の開催についてのお尋ねにお答えいたします。今回の大雪を受けまして2月には雪害対策本部が設置されたため、除雪作業会議を所管する除雪作業本部はその指揮下に入り、計画路線を優先になし得る限りの除雪対応を行ってきたところでございます。通常の除雪作業本部体制時におきましては、危機管理監制度が発足して以降、除雪作業会議に替わる危機管理連絡会議におきまして、市民生活関連を含めます関係課の間で効率的な除雪作業を行うため、予想される事態やその対策に関する情報の共有を実質的に図っておりますので、従来の除雪作業会議は開いていないものでございます。今後こうした会議の在り方につきましては、除雪計画の見直しの中で改めて検討して参りたいと考えております。
-太田 副支局長
介護保険料の減免制度についての実績のお尋ねがございました。平成28年度におけます介護保険料の減免件数は95件でありまして、このうち生活困窮を理由とした減免の件数は54件でございます。
次にボランティアポイント制度の主旨・内容についてのお尋ねでございました。この制度は高齢者が地域における福祉活動の担い手となるとともに、ご自身の健康づくりや生きがいづくりにも繋げていただきますよう、ボランティア活動への参加の動機付けとして実施するものでございます。ボランティアの登録申請をされました65歳以上の方が市内の特別養護老人ホームにおいてボランティア活動を行った際にポイントを付与し、200ポイントを貯めた場合に協賛店舗で優待サービスが受けられます「金沢元気わくわくクーポン」を交付するものとなっております。
最後に、第7期の特別養護老人ホームの整備計画のお尋ねです。第7期におきましては上荒屋と大手町の各日常生活圏域で定員29名の地域密着型特別養護老人ホームをそれぞれ1施設ずつ整備することとしております。
-野口教育長
教職員の長時間労働と対策についてお尋ねがございました。
初めに本市小中学校の教職員の勤務の実態についてお答えします。平成29年4月から12月における教職員1人当たりの時間外勤務時間は1カ月平均で、小学校で48時間51分、中学校で74時間18分でございました。また時間外勤務時間が厚生労働省労働基準局長通達に定める長時間の過重業務とされる月80時間を超える教職員の割合は、小学校で13.1%、中学校で43.1%でございました。
次に長時間勤務をなくすための対策についてでございますが、先般、教育委員会議におきまして本市の教職員が本務に専念するための時間の確保に向けた取り組み方針の素案を報告を致したところであります。その中では長期休業中の学校閉庁日の設定や、学校事務補助職員の配置拡充、部活動休業日の拡充など、教育委員会や学校がそれぞれ行う具体的な取り組みを示しました。県教育委員会が示す教職員の多忙化改善に向けた取り組み方針も踏まえ、明年度からこれらの取り組みを実施していきたいと考えています。また、教員の長時間勤務について、抜本的な改善のためには教職員定数を増やすことが必要だと考えるがいかがか、というご質問もいただきました。素案にも示してございますが、教職員が本務に専念するための時間の確保に向けた抜本的な改善には、議員も仰せの通り国による教職員の定数改善が不可欠であり、中核市教育長会などを通して引き続き国に働きかけていきたいと考えております。
次に学力テストについてご質問がございました。授業は年間計画に基づいて行われておりまして、本市におきましては、これまでのこの本議会での議論なども踏まえながら、学力テスト直前には特別なことは行っていないと思っております。今後も各種学力調査が児童生徒の学力の状況を把握し授業改善に役立てるという目的に沿って実施されるように指導して参りたいと考えております。
お尋ねのありました、県基礎学力調査につきましては、石川県教育委員会が児童の学力の定着状況及び学習・生活状況を把握することを目的に、平成14年度から実施しているものであります。その結果は2年後の第6学年で実施する「全国学力学習状況調査」の結果等と比較し、課題が改善されているか検証するなど、学校における児童への教育指導に有効な手立てであると考えております。
最後に、本市のいじめの対策についてお尋ねがございました。いじめの対策につきましては、未然防止に努めることが肝要であると考えておりまして、本市では悩みを持っているこどもたちを見逃すことがないように各学校で個人面談や定期的にアンケートを実施することで実態把握に努めております。また「学校いじめ防止基本方針」をもとに校内のいじめ問題対策チームが中心となって学校全体で適切な取り組みがなされるよう指導しているところでございます。加えて、悩みを抱える児童生徒への対応として、専門的な立場から適切な助言を行うスクールカウンセラーを来年度から市内全ての小中学校に配置を予定しております。引き続き、いじめの未然防止及び早期発見とその対応に努めていきたいと考えております。
-30番 森尾嘉昭議員
市長に伺いたいと思いますが、大桑議員が指摘して取り上げたように、今年から第7期の介護保険事業計画が始まります。その中の施設整備計画が示され、本市において小規模特別養護老人ホームを今後3年間で58床整備するとしています。小規模ですから29床とすると2か所の整備という整備計画となろうかと思います。ところで市長は選挙の際に出されたマニフェストの中で特別養護老人ホームの待機を失くしますということを掲げられました。今回の整備計画で待機者はなくなるのでしょうか?
-山野市長
一期目の選挙のときに公約に掲げさせていただきまして、担当部署や関係機関と連携を取りながら精一杯取り組んできたところであります。まだまだその目標には届いておりませんけれども、引き続きその旨を持って取り組んでまいりたいと考えております。
-森尾議員
では福祉局長に伺いたいと思います。今回から始まるのが第7期、それ以前の3年間が第6期です。この第6期で小規模の特別養護老人ホームの整備計画は3年間で9か所、261床を整備するとしました。今回第7期は2か所、58床というのが打ち出されています。それでは本市における特別養護老人ホームの待機者数というのはどのくらいとして把握しているのでしょうか。そして6期に比べて大幅に整備計画が少なくなったのはどういう考え方となったのでしょうか。
-太田福祉局長
本市におけます待機者数、正確な数字は今持っておりませんが、おおよそですが400人台というふうにとらえております。これは県の調査も踏まえまして本市独自にも調査をしまして、各事業所全てに聞き取り調査をした結果であります。待機者数の中には、とりあえず今必要はないけれども申し込みをしている方もいらっしゃいますし、すでに他の施設に入られた方もいらっしゃいます。そういった方々を除外しますと、500を少し切るくらいの数でございます。一方で現にあります特別養護老人ホーム、こちらでそれぞれ空床がございます。空床は多い少ない多少の差はありますけれども、そういった空床の数も全て調査をいたしました。待っていらっしゃる方、それから開いているベッドの数、それではやはり足りませんので、足りない数を計算したところ約2施設、58床という数字が出たものであります。